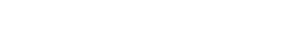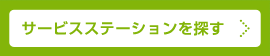Vol.03ジャズオーケストラ
ジャズでは希少なホルン吹きです。

安藤 友祐/経理部電算課
PROFILE
高松市出身、2000年入社。
主に情報システム業務担当。お客様と従業員の気持ちを理解・実現できる裏方を目指し修行中ですが、まだまだ道程は遠い!
写真は愛器Yamaha YHR881と。

-

SWJOの弟分で、ジャズの啓蒙・育成を目的とするバンドKagawa Student JAZZ Orchestraにて、小編成(コンボスタイル)でアドリブ中の図。まだアドリブ経験の場数が少なく、本番になると写真のようにがちがちに緊張します。若葉マークです。
高松市の'Speak Low'にて -

Live at Blue Note NY
(2001/01/02) -

Live at Jazz @ Lincoln Center
センターの歌手は伊藤君子さんです。
(2006/01/02) -

穐吉敏子さん、Lew Tabackinさんご夫婦を囲んで関係者大集合!
「大成功万歳!」
(2008/05/25)
今年で参加満10年。ジャズビッグバンド・SWJOで年間数十回の公演活動を行っています。
私はアマチュアのジャズオーケストラ(ビッグバンドと言います)に所属しています。楽器はホルン(フレンチホルン)を吹いています。というと、皆さん一様に「へえ?」という顔をされます。ホルンは元々クラシックや(クラシックオーケストラはVol.04の渡邉君ご参照)吹奏楽では大活躍する楽器。ジャズといえばサックスにトランペット、ピアノなどを思い浮かべる方は多いと思いますが、ホルンを思い浮かべる方は皆無だと思います。
中学入学の時、近所の先輩に連れて行かれた吹奏楽部。人がいないという理由だけでホルンを握らされました。高校は希望の学校に行けず、部活のない高校に進学しましたが、それが音楽への情熱に火を付けました。こうして大学では入学式より前に吹奏楽団に入り、どんどんとのめり込んでいきました。
時を同じくしてClifford BrownやWayne Shorter、Jazz Messengersをヘビーローテーションする先輩の影響を強く受け、ジャズをやりたいという気持ちを強く持ち始めました。でも聴くのと演奏するのは大違い、多くのジャズを本格的にプレイしたいホルン吹きは迷います。他の金管楽器と大きく異なり、技術的・歴史的背景から、この楽器でジャズを中心にプレイしている人が殆どおらず、特に日本ではプロアマ併せて数十人といないようです。教則本など、ネットで血眼になって探しても2、3点という有様です。殆どのジャズをやりたいホルン吹きが、ホルンに見切りを付けて他の楽器へ転向していくか、ホルンを吹き続けるためジャズを中心に演奏することを止めます。そんな私もトランペットへの転向を考え始めました。
大学を卒業し、地元香川へと帰ってきたとき、高松のジャズビッグバンド・Swingin' Wonderland JAZZ Orchestra(SWJO)の存在を知りました。何とホルン吹きの方が在籍されており、実際に演奏されているではないですか。直談判で無理矢理お願いして仲間に入れていただき、遂にジャズでホルンを演奏する道が開けたのでした。
しかしそれからが大変でした。難しいどころか、全く吹けません。ただでさえ私の譜面の読みが遅いのに(その上ホルンの譜面自体がないことが多いため、調の違うトロンボーンの譜面を読んでいるので尚更)楽器の特性上、ジャズに求められる発音や音の立上がり・切れの鋭さがなかなか出ないのです。どうにか吹けたところで皆と合うべき音が合いません。バンドのレベルに全く付いて行けず、長年足を引っ張り続け、正直もうだめだと思うことも何度となくありました。でもバンドの皆さんは気長に私の成長を待って下さいました。お陰様で今年、参加満10年を迎える事ができ、今やっとスタートラインに立てたかなという感がしております。
さてその間、香川芸術フェスティバルJAZZ部門のバンドだったSWJOは2004年にNPO法人として独り立ちを果たしました。バンドマスター・関元直登氏の強力なリーダーシップの下、これまで3度のニューヨーク公演、レイ・パーカーJr.や穐吉敏子各氏をはじめとする国内外トップミュージシャンとの共演、演劇等とのコラボレーションを次々と実現し、一方、国民文化祭出演・国際会議レセプションから商店街の街角コンサート・町内夏祭りまで年間数十回に及ぶ出演の他、高校生や社会人にジャズを広めて行くことも積極的に行っています。また近い将来、高松で大きなジャズフェスティバルを開催する構想も進行中です。
アマチュアバンドゆえメンバーも皆自営業・公務員に会社員・主婦・父親・学生とそれぞれ生活の基盤となる「普段の顔」を持っています。本番回数が非常に多く、有名ゲストを迎える大きな公演がコンスタントにあるSWJO、時にはそんな「普段の顔」との両立に苦しみます。でも、やはり「普段の顔」を取り巻く方々の強力な支えあってこそ、活動に励めていることも皆常々感じていることです。音楽の力で、自分たちだけでなく、そんな「普段の顔」の皆様へ、常日頃から物心両面でバンドを支援していただいている方々へ、地域の人たちへ、日本中へ、遂には世界の人たちへ少しでも希望や元気を発信できればという想いを持って、これからも頑張ります。